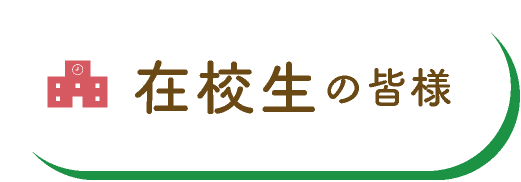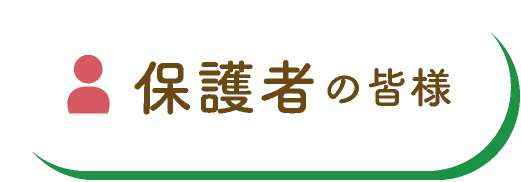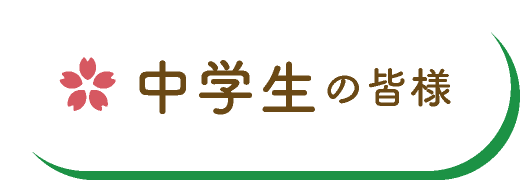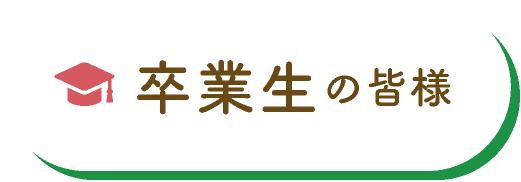校長のひとりごと R7.10.10
2025年10月10日
※「ブラックボックスの蓋を」
先週末に出会った方から「校長のひとりごとがしばらくアップされていませんね」の一言。忙しさ等もあったが、忘れていたわけではなく、それ以上にピピッとくるものが思い浮かばなかったというのが事実。
さて、今週はノーベル賞ウィーク?。毎日受賞者が発表され、本日(10/09)時点で日本人は2名の方が受賞されている。しかし「人を幸せに、人に役立つもの」とされるその素晴らしさに私の理解が追いつかない。「制御性T細胞」は解説を見て、ぼやっとイメージが浮かんだが、「多孔性金属錯体」はうーん??の状態。このようなニュースに触れたときは「学生時代にもう少し、勉強しておけばよかったのかな」と後悔ばかりである。
確かに私が子どもの頃と比較しても、「人を幸せに、人に役立つもの」づくりは進み、世の中は便利に、そして生活の幅が広がった。思い浮かぶものを並べてみると「テレビ」「電卓」「ビデオ」「CD」「ゲーム機」「携帯電話」「パソコン」「ワイヤレス○○」「スマホ」「BS・CS放送」「LED」「ハイブリッド車」「電気自動車」等々。だが、これら製品が「なぜそれができるか」の理屈がわかるかと言えば、大半はブラックボックスだと思う。わかりやすいテレビを例にすると、テレビがなぜ映るのかを説明できる人は多くはない。しかし、テレビの電源を入れ、見たい番組にチャンネルを合わせることはまずだれでもできる。つまり内容や仕組みを知らず、その効果≒便利さを利用している実情をブラックボックス化現象とよぶ。先に挙げたスマホやパソコンなども同様であろう。
技術の進化は私たちに機能的(「軽い」「安い」「かんたん」など)、情緒的(「嬉しい」「楽しい」)といったベネフィットを与えてくれている。だが、これを生み出すにはそもそもの「内容」や「仕組み」がまず考案される必要がある。学校の勉強は皆にベネフィットを与える場面は少ないかもしれないが、「なぜ」「どのように」を考えるチャンスであると思う。ブラックボックスの蓋を少し開けてみませんか。自己実現のきっかけになったりするかも・・・。