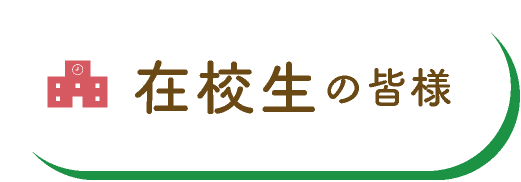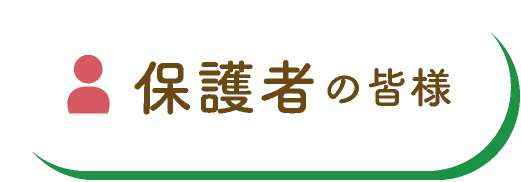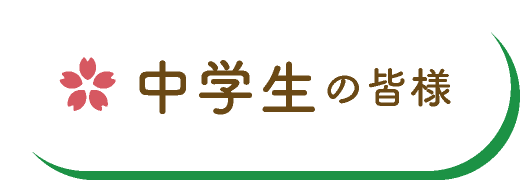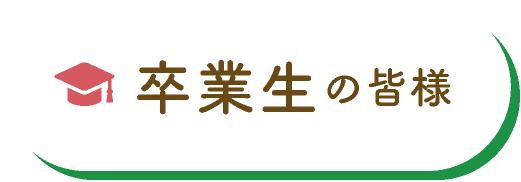校長のひとりごと R7.7.11
2025年07月11日
※「体験に勝るものなし」
学校というところでは多くの「○○教育」と名付けられたものを推進することが求められている。多くの「○○教育」があり、先生方は教科の教育以外に、各教科の活動や総合的な探究の時間などに盛り込みながら、指導してくれている。恥ずかしながら「〇〇教育」はたくさんありすぎて、私もトータルいくつあるのか明確には答えられない。
いくつあるのか、調べてみると「租税教育」「法教育」「防災教育」「命の教育」「STEAM教育」「情報教育」「ICT教育」「著作権教育」「ネットリテラシー教育」「プログラミング教育」「人権教育」「主権者教育」「平和教育」「消費者教育」「環境教育」「金融教育」「キャリア教育」「心の教育」「国際理解教育」等々、挙げていけば有に50は超えそうである。どの内容もこれからの世の中を生きていく生徒たちにとっては大切である。とは言え、現場としては実施時間確保からして困難であり、加えて先生方の指導研究も追いつかない。外部専門講師に依頼する方法もあるが、内容が専門的すぎて生徒たちの実態と乖離し、理解が追いつかないケースもあった。総じて言えば、これまでの実施においては、知識としての定着はある程度確認できるが、「わがこと」として落とし込めているかは甚だ疑問であると判断できる。というのも、「○○教育」の実施については総じて「体験を伴うことによって、学びの質が向上する」傾向があると感じているからだ。
「主権者教育」に絞れば、最近は本当の選挙と同時開催の模擬選挙を通じ、こどもたちへ「リアルな学び」と「地域社会への参加機会」を提供する「こども選挙」の取り組みが増加している。しかし、開催されるエリアや参加者数が限られている現状も否めない。もう少し、身近な体験はないのか? 公職選挙法の改正により、平成28年6月から投票所に同伴できる子どもが「幼児」から「18歳未満」に拡大された。子どものときに保護者と一緒に投票所へ行ったことのある人は、行ったことのない人と比べて、有権者になったときの投票率が高いという調査結果が出ている。【H28年総務省18才選挙権に関する意識調査】保護者とともに投票所に向かうということ、その場の雰囲気を感じること、これも貴重な「体験」ではないだろうか。「主権者教育」に限らず、保護者の皆様には子どもたちに“プチ+様々”な「体験の機会」を与えていただければ幸いである。