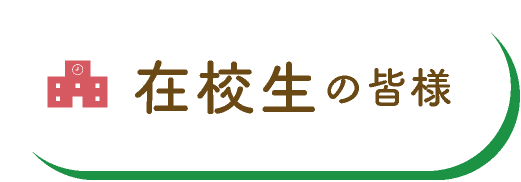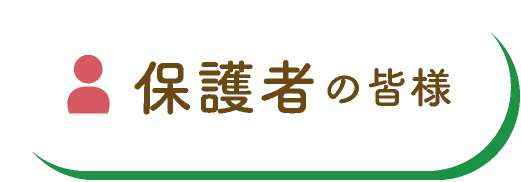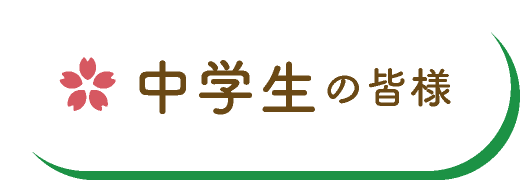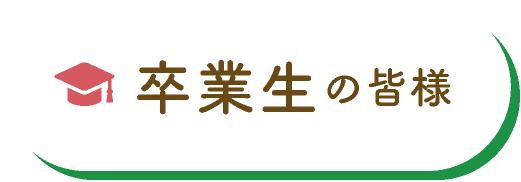校長のひとりごと R7.2.26
2025年02月26日
※「フィルターバブル現象」
卒業式も近づき、3年生のことを考えながらふと思い浮かんだこと。
先日、スマホで1度子猫の動画を見たら、翌日からgoogleやyahooの初期画面に似たような記事や動画項目が表示されはじめた。また、同様に「テレビ24型」と検索したあとに、やたらとテレビ商品の広告が表示されるようになった。いわゆるトラッキングという仕組みによって、自分の検索履歴を覗いているかのような状況であり、同時に「あなたの興味あるものを示していますよ」というある意味余計なお世話でもある。これに気づかず、閲覧を続けていれば「自らの興味の幅が狭まり」や「情報収集が偏る」等の可能性は否定できない。
私は30年以上にわたり、授業に新聞を活用してきたが、その理由は「新聞の一覧性」であった。確かに授業で活用する部分はひとつの記事やグラフ等だけなのだが、その周りにある記事、あるいは目的の記事に到達するまでの「めくる」という行為によって、自らに興味のなかった見出しや写真に目がとまり、新たな気づきが生じる可能性もある。図書館や書店にお気に入りの1冊を探しに行ったが、棚に並ぶ多くの本のタイトルや帯に目がとまり、気づけば数冊手にして帰るというのも似ているのではないか。
現代人は気がつけば、限られたネットワークからの情報に依存しているという調査結果もある。いつの間にか自らのお気に入りの情報に囲まれ、他の情報には思いが及ばなくなるといういわゆるフィルターバブル現象が顕著になりつつある。現状のSNS利用やネット検索は便利ではあるが、使い方によって自分の志向と合う情報に依存し、意見が異なる相手に歩み寄ろうとせず、簡単に判断してしまおうとする傾向も強くなる。未来を生きる生徒たちには「興味の固定化」「偏った情報への誘導」「コミュニケーション能力の低下」等のデメリットも考えられる。結果そのことが「自分さえよければ」につながってしまうことは避けたい。
巣立っていく生徒たちは先の見えない時代を生きていく存在であるからこそ、幅広な情報を獲得し、自身の興味・関心に気づき、これからを考えてほしい。地域協働学習により、本校生徒は地域の方々とのコミュニケーションも体験している。自分と異なる価値観にも触れることを止めずに、一歩ずつライフプランを構築してほしい。